Le Temps des Cerises
原題は「さくらんぼの頃」の意味。 日本でも『さくらんぼの実る頃』のタイトルでよく知られた往年のシャンソンの名曲である。
ジャン=バティスト・クレマン(Jean-Baptiste Cle´ment)作詞(1866年)、アントワーヌ・ルナール(Antoine Renard)作曲(1868年)による。 現在まで歌い継がれているシャンソンの中で最も古い曲だといわれている。
さくらんぼにことよせて、若き日の恋の思い出を、甘酸っぱく歌い上げている素朴でノスタルジックな内容だが、この曲について語るときはいつも、パリ・コミューンとの関連がクローズアップされてくる。 まずは、それも含めた曲の背景を簡単にまとめてみたい。
<パリ・コミューン>
普仏戦争(1870年〜1871年)で敗れたフランスは、ナポレオン3世の第二帝政が終焉し第三共和政に移行する。しかし、プロイセンとの和平交渉に反対し自治政府を宣言した労働者政権のパリ・コミューン(la Commune de Paris 1871)は、1871年3月18日から同年5月28日までの短期間パリを支配した。
これを鎮圧しようとするヴェルサイユ政府軍との激しい市街戦の後、パリを包囲した政府軍によってコミューン連盟兵と一般市民の大量虐殺が行なわれた。

「血の一週間(la semeine sanglante)」と呼ばれるこの戦闘により、3万人にのぼる戦死者を出してパリコミューンは瓦解し、5月27日ペール・ラシェーズ墓地での抵抗と殺戮を最後にこの戦いは幕を閉じた。
この戦いが勃発し、そして無残な結末を迎えた時期が、まさに<さくらんぼの季節>でもあり、この事件後に成立した第三共和政に批判的なパリ市民たちによって、1875年前後から、連盟兵たちへのレクイエムであるかのように、この歌が繰り返し歌われたことから「パリ・コミューンの音楽」として有名になったのだと伝えられている。
|
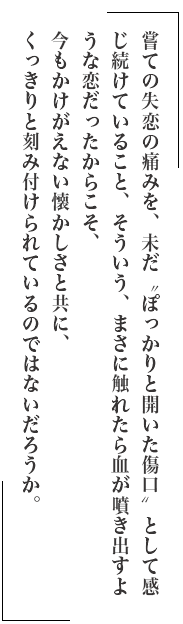 |
蛇足であるが、パリ・コミューンゆかりの地、モンマルトルの丘に今も残る老舗のシャンソニエ「ラパン・アジル」を数年前に訪れた時、偶然だがこの「Le Temps des Cerises」が歌われて、これに唱和する観客に交じって私も声を合わせたことを懐かしく思い出す。長い時間の中を生き続けてきた曲であることが再認識される。
<ルイーズとの出会い>
さて、作詞者のクレマンは自身も連盟兵として戦ったのだが、その折、野戦病院で負傷兵の手当てをしている一人の女性革命家と出会うことになる。
彼女ルイーズ・ミシェル(Louise Michel)の甲斐甲斐しく働く姿に大きな感銘を受けて、すでに流布していたこの「Le Temps des Cerises(さくらんぼの頃)」に、改めて「1871年5月28日日曜日、フォンテーヌ・オ・ロワ通りの看護婦、勇敢なる市民ルイーズに」という献辞を付則したのだという。
そして同時に、これまで3番までだった歌詞に、新たに4番の歌詞を加えて発表した。4番には「あの時から、この心には、開いたままの傷がある」のフレーズがあり、この曲が、パリ・コミューンへの追悼として作られたものだと解釈する所以ともなっているのだが、3番までの歌詞がパリ・コミューンの時期の数年前に既に出来上がっていたことを思えば、少しうがち過ぎで、あくまでも失った若き日の恋を思い懐かしむ曲と取るほうが自然であると思われる。
|

「血の一週間」をめぐる惨劇を目の当たりにし、この渦中に生きた作詞家クレマンの献辞は、コミューン兵士たちへの挽歌であると同時に、甘く短いさくらんぼの時間・・・・真っ赤に熟し燃え上がるつかの間の恋の情熱と、夢破れた恋の挫折、・・・そしてルイーズという優しく果敢に戦い挑む女性との一瞬の邂逅、そういう全てに手向ける言葉だったと言えるかもしれない。
「さくらんぼの実る頃」
<美しい情感>
フランスではイヴ・モンタン、コラ・ヴォケールを初め何十人という歌手がこぞって歌い継いでいるが、日本でも、シャンソンの代表的名曲として、多くの歌手のレパートリーとなっている。
訳詞も様々にあるが、よく耳にするのは工藤勉氏の訳詞かと思われる。
さくらんぼ実る頃は うぐいすが楽しそうに 野に歌うよ
乙女たちの心乱れて 恋に身を焦がすよ
さくらんぼ実る頃は 愛の喜びを 皆 歌うよ
|
という1番の歌詞から始まり、「愛する人に抱かれて胸震わせても さくらんぼが実り終わると鶯は去り 赤いしずくが胸を染める」という2番へと続く。
そして最終章の3番で「さくらんぼの実る頃は 年老いた今も 懐かしい。 あの日のことを心に秘めて、いつもしのんで歌う」と締めくくられている。
日本語の持つ情感と余韻が美しく、品格のある詩の世界が出現している。
この工藤氏の訳詞だけではなく、他の訳詞のほとんども<若き日の恋を懐かしく蘇らせながら、過ぎ行く時への感慨をかみしめる>というしみじみとした老境を歌い上げる格調高い曲というイメージが強い。旋律の美しさと合わさって、歌い手の側にも年輪を重ねた深みが要求されるのかもしれない。
1992年には、加藤登紀子氏が、スタジオジブリのアニメ映画 『紅の豚』の中でフランス語でしみじみと歌われていて、この曲の知名度を上げた。

<「血が滴る」と「傷口が開く」について>
先にパリ・コミューンとの関連について述べたが、このような、いわば隠喩を用いた反戦歌と思われた理由の一つに、ちりばめられている「言葉」そのものがあるのではと私は感じている。
さくらんぼが実っている描写を記した2番の詩句
Des pendants d'oreilles
Cerises d'amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang
耳飾り
お揃いのドレスを着た愛のさくらんぼ
血のしずくが葉陰に滴り落ちている
|
(対訳) |
そして現在まで続く心の痛手を歌った4番の詩句
J'aimerai toujours le temps des cerises
C'est de ce temps-la` que je garde au coeur
Une plaie ouverte
私はずっとさくらんぼの季節を愛し続けるだろう
開いた傷口を
心の奥に持った季節なのだから |
|
(対訳 ) |
|
|
|
![]()
![]()