ゾラの長編小説「居酒屋」を思い出してしまった。
健気で働き者の洗濯女ジェルヴェーズが、平凡な幸せを夢見て苦境に立ち向かってゆくのだが、過酷な運命と貧困とに翻弄され、ついには自らも自堕落な生活に転落し、絶望の中で、無残に死にゆくという物語で、人間は、その人格も倫理観も幸不幸も、全ては社会環境によっていかようにも変化し得るものだ、というゾラ特有の自然主義哲学が貫かれている作品だ。
この小説はこれまでに何回も読んでいるが、それにしても話の展開や描写が、余りにも救いがなく悲惨すぎて、いつも最後まで読むのが辛くなってしまう。
フランスに限らず日本でも、長い歴史の中で、家族を救うため身売りする女の子たちの実話は山の様にあるし、現実は小説より更に悲惨なはずで、戦争や貧困のもたらす悲劇を思うと胸塞がれる。
<Dans ma rue>の最後のフレーズに、祈りの様に語られている「神様が温めてくれる」という言葉に胸を打たれる。
「天使」や「神」という言葉に西洋的な匂いを感じるが、私の訳詞では、「神」や「天使」を繰り返すことは敢えて避け、
神様の元に こうして向かう
の一言だけで万感を表してみた。
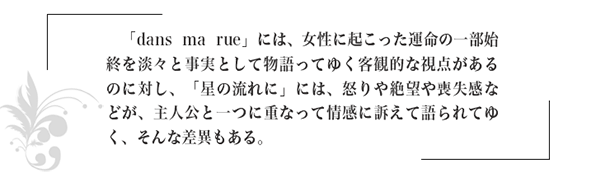
星の流れに・・・・
終戦記念日が近づくとテレビ、ラジオ、新聞などでも、戦後の歴史を改めて辿り、思いを馳せる様々な特集などが組まれる。
先日、戦後の歌謡史とその時代背景を重ね合わせて語るテレビ番組を観た。
その中で、1947年(昭和22年)のヒット曲、「星の流れに」を取り上げていた。
「終戦で、奉天から単身引き揚げてきた従軍看護婦の女性が、東京の焼け野原の中に一人置かれ、働くすべもなく、飢餓状態に陥った末、ついには娼婦へと身を落としてしまった」・・・その女性が自らの転落の顛末を手記にして新聞に投稿した、その記事に触発され、彼女をモデルに作られた曲なのだそうだ。
最初は「こんな女に誰がした」というタイトルで発表されたのだが、日本人の反米感情を煽る事になると、GHQからクレームがきたため、急遽「星の流れに」というタイトルに変更されたのだという。
星の流れに 身を占って 何処をねぐらの 今日の宿
荒(すさ)む心で いるのじゃないが 泣けて涙も 涸れ果てた
こんな女に誰がした (1番のみ)
「Dans ma rue」は1946年、そしてこの曲は1947年、ほぼ時を同じくして東西で歌われた曲に、同様の心境を感じるが、しかし一方では、「dans ma rue」には、女性に起こった運命の一部始終を淡々と事実として物語ってゆく客観的な視点があるのに対し、「星の流れに」には、怒りや絶望や喪失感などが、主人公と一つに重なって情感に訴えて語られてゆく、そんな差異もある。
フランスのシャンソン、日本の歌謡曲のそれぞれが持つ典型的な特徴の一つを見るような気がしてとても興味深く思われる。
「この路地で」が、古くて新しい、心に沁み入る歌として、共感を持って受け止めていただけるようになればと思う。
Fin
(注 訳詞、解説について、無断転載転用を禁止します。
取り上げたいご希望、訳詞を歌われたいご希望がある場合は、事前のご相談をお願いします。) |
![]()
![]()